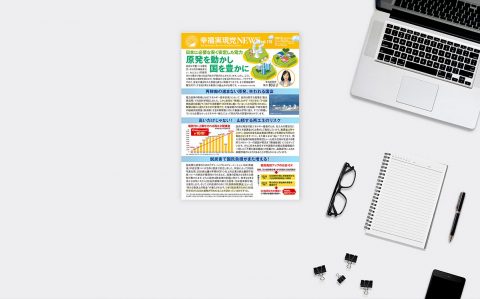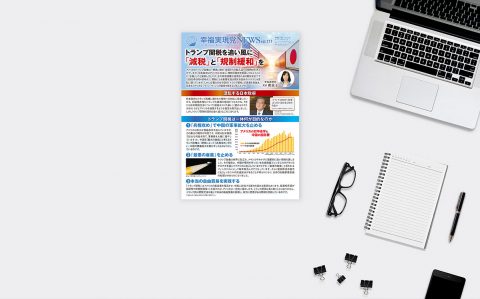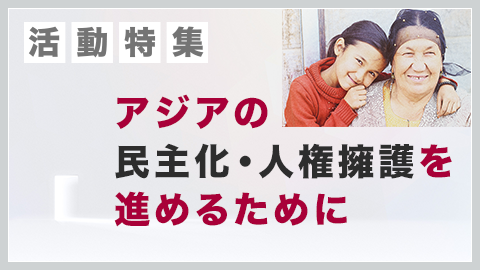8月25日(月)、長崎県大村市 光山千絵議員、佐賀県鹿島市 釘尾せつ子議員、中島徹党佐賀県本部統括支部代表が、長崎県知事宛、県議会に対し、パートナーシップ宣誓制度の導入を反対する要望書と陳情書を提出いたしました。
LGBTQの方々に対して、差別や偏見、迫害などは絶対にあってはならないものであり、偏見などを無くすための人権保護は、当然行うべきものです。
しかし、人間の性に関する価値観は人それぞれ違うことから、その判断は個人や家庭に委ねられるべきものです。
近年の欧米の例を見ても、LGBTQの方々への過度な権利保護は、言論の自由の制限や男性・女性の権利の侵害など様々な社会問題を生み出し、逆にLGBTQへの差別意識の高まりと社会的対立をもたらしております。
現状では県内でパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体は3市町であり、一部の方々だけで議論された前述の検討委員会の意見とりまとめを重視した決定は問題があります。県としてのパートナーシップ制度の導入の是非については、県全体で十分かつ慎重な議論をして対応すべきものであり、軽率に本制度を導入することは避けるべきと考えます。



左から、中島徹党佐賀県本部統括支部代表、佐賀県鹿島市 釘尾せつ子議員、長崎県大村市 光山千絵議員
長崎県議会議長 外間 雅広 様
「パートナーシップ宣誓制度」導入に関する陳情書
提出者 幸福実現党 長崎県本部
代表 才田 明
1.陳情の趣旨
県が昨年度設置した「長崎県人権施策のあり方に関する検討委員会」の意見とりまとめを受け、大石知事は6月20日の県議会一般質問において、LGBTQら性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を令和8年度の早い時期に導入する考えを示しました。
本委員会ではパートナーシップ宣誓制度の意義として、「異性間の婚姻は、法律に基づく様々な権利や利益を享受できるが、同性カップルは法律上の夫婦になることができないため、同様の利益を享受することができない。また、当事者にとって、性的指向は自分で選択できるものではないにもかかわらず、この不平等を受け入れざるを得ない状況にある。パートナーシップ宣誓制度は、法律上の夫婦が利用できる制度の一部を、パートナーシップを宣誓したカップルに対しても適用することで、この不平等の解消を目指すものであり、県はパートナーシップ宣誓制度を導入する方向で検討したほうがよい」としています。
確かに、年々、多様な性の在り方を認めようとする動きは強まっておりLGBTQの方々への理解が進み、人権が尊重されることは当然の事とは考えますが、国内外ではLGBTQの方々の権利拡大や行き過ぎた保護が少子化・人口減少・家族制度の希薄化に繋がるのではないかと危惧する意見も出ています。また、様々な社会的問題が起きており、LGBTQの方々への支援の在り方は慎重に議論すべきものと思われます。
国内では女装した男性が女子トイレに侵入し、盗撮しようとしたなどとして逮捕される事件が発生しています。本事件の犯人は逮捕時に「心は女」との主張をしており、それを口実として女性の安心安全が脅かされることはあってはならないことです。同様の事件は多数発生しておりますが、心が男性か女性かは客観的に判断できないことからLGBTQの方々への過度な権利拡大は多様な考え方を持つ県民にとっての生きやすい社会から逆行することに繋がりかねません。
このような考え方に対し「差別と偏見に基づく発言だ」と一方的に論じる意見もありますが、問題を指摘すること自体がLGBTQの方々に対する無理解や差別だと言われるようでは、民主主義国家としての思想・信条・言論の自由が侵害されてしまうのではないかと極めて憂慮しているところです。
また、婚姻制度とLGBTQとの関係について憲法学の専門家である長崎大学の池谷和子准教授は、婚姻を「社会的な制度」とみなして、「結婚とは子どもや社会の利益のために、カップルによる性行為、出産、子育てを社会的に承認するもので、生まれてくる子どもの福祉、実の親との安定した親子関係を保護することを第一義的目的とする制度と解釈すべきではないか。このように子どもの観点からみれば、法が同性婚と異性婚を同等にすべきではないと思われる。同性婚とは異なる制度とは言え、現在各地の自治体で進められている同性パートナーシップ制度が広がっている状況についても、子どもたちの健全育成、家庭の保護が脅かされるのではないかと大変憂慮している。」と述べられています。
LGBTQの方々に対して、差別や偏見、迫害などは絶対にあってはならないものであり、偏見などを無くすための人権保護は、当然行うべきものです。
しかし、人間の性に関する価値観は人それぞれ違うことから、その判断は個人や家庭に委ねられるべきものです。国内外を問わず、宗教によっては、同性間の性行為を「罪」としたり、無宗教でも伝統的な道徳観等の思想信条から否定的に考える人も少なくありません。このような状況の中で、県がパートナーシップ宣誓制度を導入して住民の意識を変えようとすることは、憲法が保障する信条・信仰の自由の侵害につながる恐れもあるのではないでしょうか。
近年の欧米の例を見ても、LGBTQの方々への過度な権利保護は言論の自由の制限や男性・女性の権利の侵害など様々な社会問題を生み出し、逆にLGBTQへの差別意識の高まりと社会的対立をもたらしております。
現状では県内でパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体は3市町であり、一部の方々だけで議論された前述の検討委員会の意見とりまとめを重視した決定は問題があります。県としてのパートナーシップ制度の導入の是非については、県全体で十分かつ慎重な議論をして対応すべきものであり、軽率に本制度を導入することは避けるべきと考えます。
陳情の理由
県知事に対しパートナーシップ宣誓制度の導入を行わないよう要請すること
以上