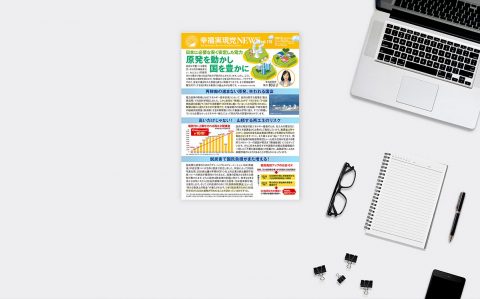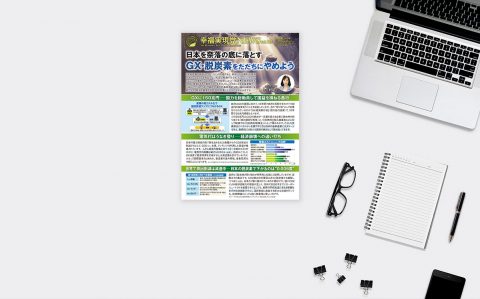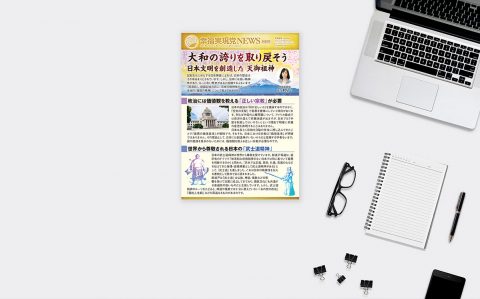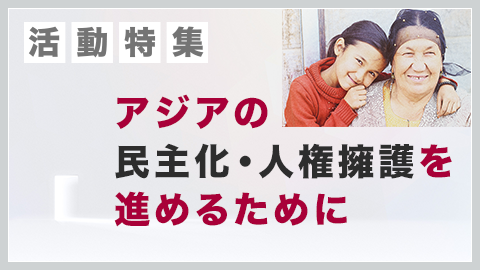2025年11月23日
幸福実現党政務調査会
No.40
高市政権の目指す「強い経済」は、国民生活を破壊する

ポイント
- 21日、政府は総合経済対策を閣議決定。減税策と併せた財政支出は21.3兆円、事業規模は42.8兆円。
- 補助金・給付金により物価高に対応するという基本的な考え方は、前政権までのものと同様であるが、歳出の一層の拡大や、コメの増産方針の転換から、物価高はむしろ深刻化する可能性がある。
- 財政状況が深刻な中で積極財政を強行する中において、財政を健全にする「責任」感が見られない。
- 物価高に対応し、「強い経済」を形成するためには、本来、「小さな政府・安い税金」の国づくりで、民間主導によるサプライサイドの強化を図る必要がある。
政府の経済対策が閣議決定
11月21日、政府は物価高対策などを柱とする総合経済対策を閣議決定しました。所得税の「年収の引き上げ」「ガソリン税の旧暫定税率の廃止」などの減税策と併せて21.3兆円(うち、補正予算案の一般会計歳出は約17.7兆円程度の見込み)、国、地方自治体、民間資金を合わせた事業規模では42.8兆円規模となっています。
今回の経済対策は、①生活の安全保障・物価高への対応②危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現③防衛力と外交力の強化の3つの柱で構成されています(図表1)。
今後、政府は、対策の裏付けとなる補正予算案を今の臨時国会に提出、来月までの成立を目指すとしています。
(図表1)政府の経済対策の3つの柱
| 財政支出 | 事業規模 | |
| 生活の安全保障・物価高への対応 | 11兆7000億円 | 16兆2000億円 |
| 危機管理投資・成長投資による強い経済の実現 | 7兆2000億円 | 17兆5000億円 |
| 防衛力と外交力の強化 | 1兆7000億円 | 8兆4000億円 |
| 予備費の確保 | 7000億円 | 7000億円 |
| 合計 | 21兆3000億円 | 42兆8000億円 |
*内閣府「『強い経済』を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(令和7年11月21日閣議決定)より

政府主導の「強い経済」は、国民生活を犠牲にする
補正予算の規模は、2016年から19年までは1兆〜3兆円の規模であり、23年の岸田政権では13.1兆円、24年の石破政権では13.9兆円と歳出が肥大化し、財政はたがが外れた状態が続いてきました。今回の経済対策(補正予算で17.7兆円程度の見込み)は前年を大きく上回っており、歳出先行型の財政のあり方にアクセルが踏み込まれた形となっています。
政府がこの経済対策を策定するにあたり、自民党内などからは、「金額は前年を上回るべき」といった声も出ていました。高市早苗政権は「責任ある積極財政」を掲げてきましたが、財政規律を顧みず、単に「規模ありき」の対策となっているのであれば、大いに問題があるでしょう。
今回の経済対策は金額規模で見ると半分以上が物価高に割かれています。現在、内閣府や民間シンクタンクの試算では需給ギャップはプラスの値を示しており、需要が供給を上回る状況となっています(*1)。こうした状況で財政出動を行えば、物価高はむしろ悪化することは自明のことであり、「規模ありき」の議論が進んでいたのであれば、ナンセンスであると言えます。
尚、内閣府が17日、7-9月期の実質GDPが年率換算で1.8%減となると発表しました。これは主にトランプ関税による輸出減と住宅投資の落ち込みによるものですが、対米輸出については、既に下げ止まりの動きを示しているほか(*2)、住宅投資の減少については、2025年4月の建築基準法・省エネ法改正によって、住宅建設、大規模リフォーム時のコストが増加するため、住宅着工が3月に前倒しされる駆け込み需要が発生し、翌期の住宅着工が大幅に落ち込んだことによるものです。いわば、今回のGDPの減少は一過性のものに過ぎず、これが大規模な経済対策を行う根拠にはなりえません。
補助金・給付金によって物価高に対応していくという考えは、前政権までのものと何ら変わりはありません。今回の対策では、家計への対策として、子育て世帯に18歳以下の子ども一人当たり2万円の給付や、電気・ガス料金の7000円程度の補助(2026年1月〜3月)のほか、ガソリン税の旧暫定税率の廃止に向けた補助金の段階的な引き上げといった、給付金・補助金策のオンパレードとなっています。歳出の一層の拡大傾向を見れば、むしろ物価高はより深刻度を増すかもしれません。
財政支出のツケは増税または物価高という形になって現れます。近年は、実態に即した生活水準の指標である「実質可処分所得(*3)」の値は、低下傾向を示しています。政府が「物価高対策」と称してバラマキを行ったところで、国民生活は一向に豊かにならないことを示唆しています(図表2)。物価高に対して「対策」と称してバラマキを行い、物価高を助長させて政府の「支援」を合理化しようとすることは、政府による自作自演に過ぎません。
また、物価高は政府にとっては税収が上振れにつながるほか、債務の負担が実質上軽減するため、物価高を好む傾向があります。さらに、後述の通り、現政権では低金利を志向する傾向もあります。円安は一部輸出企業にとっては収益拡大や株価上昇につながりやすいというメリットがあるものの、輸入物価高騰とその物価全体への波及により、消費者はダメージを被ることになります。つまり、円安・物価高は政府など一部にとってはメリットを享受できる面もありますが、消費者がそのツケを払わされているのです。つまり、高市氏が目指す「強い経済」とは、国民を犠牲にする道であると言えるのではないでしょうか。
(図表2)実質可処分所得の推移

*総務省統計局「家計調査」より作成。
政府は、「政府効率化局」を立ち上げ、「租税特別措置や補助金を見直す」とうたうほか、政権与党としても、国会議員定数削減に取り組むとしています。効果の薄い無駄な歳出をカットしようという考え自体は良いとしても、「減量もやっている」という単なるイメージアップのためであってはならず、あくまで健全財政に寄与するものでなくてはなりません。今後、特に、構造的赤字を生み出している社会保障のあり方そのものにメスを入れられるかどうかが、大きな資金石となるでしょう。
高市政権の財政規律に対する認識の危うさ
高市首相は、最近こそ、日銀に対して利上げを牽制する姿勢は影を潜めていますが、2024年の自民党総裁選で「今、金利を上げるのはアホやと思う」と発言するなど、利上げには否定的な姿勢を示してきました。高市氏としては、積極財政を敢行するための国債を発行しやすい環境として、低水準の金利を維持したいという思惑があるのは論を俟ちません。しかしながら、財政出動を積極化するために低金利環境を維持できるかは、国債に対する市場の信任が担保されていることが前提となります。
高市首相は、施政方針演説において、「債務残高対GDP比」を引き下げて財政の持続可能性を実現するとしていますが、高市氏はこれまで、債務残高から金融資産残高を差し引いた「純債務残高」をGDPで除した「純債務残高/GDP」を財政健全化の目標にすべきとの考えをとってきました。今、「債務残高/GDP」は約240%(2023年)と深刻な水準に達していますが、「純債務残高/GDP」という指標で見れば、G7中最悪の値であることに変わりはないものの、約136%にまで低下することになります。
一見すれば、指標を変えるだけで、債務状況は最悪を免れているようにも見えますが、これを財政健全化に向けた目標値として適切と見るかどうかは、また別の問題となります。一例を挙げると、政府の持つ金融資産には、国民から年金保険料として預かった年金積立金などが含まれていますが、本来、年金積立金は債務返済に充てる性質のものではないでしょう。そもそも、政府が財政健全化目標の水準を変えたところで、客観的に見て日本の国債が信用に値するとみなされなければなりません。
高市政権は、PB黒字化目標について、達成状況を単年度ごとに見るのでなく「数年単位でバランスを確認する」方針に転換するとしています。PB黒字化目標を凍結し、減税や政府投資により、一時的に赤字国債を増発したとしても、中長期的にGDPを拡大させて財政健全化を図ろうという考えでしょう。確かに、財政状況がそれほど深刻化しておらず、GDP、税収が本格的に拡大する前の一時的な財政悪化に耐えうるのであれば、そうした考え方もとりうるでしょうが、今の財政状況下で積極財政を採れば、一時的な赤字幅の拡大が国債の暴落を呼び込み、財政が火の車となる危険性も完全に否定することはできず、財政を健全に運営する「責任」感は見出すことはできません。
場合によっては、2022年に英国で生じた「トラス・ショック」と同様、規律を欠いた財政政策の姿勢が国債利回りの急騰を招く可能性もあります。現に、現在、円安とともに債権安の傾向が続いています。市場が高市政権の財政は危ういと判断し、国債金利が上昇し続ければ、少なくとも積極財政を実施するための環境が整わないことになります。一部には、日本は当時の英国とは違って、経常黒字国であり、また、対外純資産を有していることから、日本でトラス・ショックは起きないとする見方もありますが、長期的に見れば、国家がさらに成熟化して経常赤字に転落する可能性もあるほか、日本の対外資産はすぐに現金化できるわけではないものが多く含まれていることから、今のような財政上の構造的赤字が続けば、日本も遅かれ早かれ、英国と同様の憂き目に遭うことになるでしょう。
やはり、本来は、政府の無駄な仕事を減量して、歳出を税収の範囲内に収めるよう努めるべきです。

サプライサイド強化に向けては、「小さな政府・安い税金」を
今回の経済対策では、「物価高対策」に加え、「危機管理投資・成長投資による強い経済の実現」として、AI・半導体、造船、バイオ、デジタル・情報安全など17分野に対し、7.2兆円分の財政支出を実施するとしています(*4)。
防衛や経済安全保障関連、核融合など重要な科学技術分野の基礎研究については、一定の投資を伴うことには一部合理性は見出せるでしょう。しかしながら、AI分野など本来は民間に任せるべき分野に対しても、国が積極的に関与していく姿勢に対しても是認できるのでしょうか。
まず、産業が補助金漬けとなれば、産業の自生的な成長力を減退させる事態にもつながるでしょう。そもそも、政府や官僚に「成長分野」を見出すだけの能力があるのでしょうか。政府、官僚が成長分野を正しく見極めるだけの情報を持ち合わせ、投資対象となる企業を公平に選定できるほどの智慧があるとは言えません。
政府支出を拡大すれば、その分、統計上はGDPの増大に寄与するのは事実ですが、政府支出が呼び水となって、民間投資を誘発するかどうかは定かではありません。現在、金融所得課税強化の動きも見られますが、物価高の悪化や大増税への懸念から先行き見通しが一層悪くなれば、民間投資は萎むこととなり、官主導で「強い経済」を作ろうとしても、行き詰まりに直面せざるをえなくなるでしょう。
政府投資の原資は国民負担にほかなりません。国民が政府から「投資を行うため」として税金を取られることにより、その分、国民は自由にお金を使うことができなくなり、税金が取られなければ生まれていたはずの経済効果も消失することになります。やはり、官主導の経済は、民間活力を犠牲にしているのです。「民間よりも国の方が賢く支出することができる」という考え方がとられるのであれば、それは、政府や官僚の傲慢ではないでしょうか。
物価高への対応だけではなく、安全保障強化の観点からも、強い農業・エネルギー体制を構築することも重要です。農政においては、「生産はあくまで需要に合わせる」として、前政権で掲げられていたコメの増産方針を一転させて、改革はむしろ後退してしまっています。方針転換の背景に、自民党が農業票を失いたくないとする策略があるのであれば、政権与党は国民生活を犠牲にして、党利党略を優先したと言えます。経済対策では、「おこめ券」の配布を介して、コメ価格高騰に対応しようとしていますが、中長期的にコメの生産が停滞し、価格が高くなるトレンドが続くと予想されることから、おこめ券の配布などは焼け石に水に過ぎません。むしろ、おこめ券によって需要が高まれば、価格が上昇することにもなります。
実質上の減反政策により高水準のコメ価格が継続し、それを補助金でカバーしようとするのは、国民に二重の負担を強いているのと同じです。減反を早期に廃止するとともに、大規模化を進めるなど農業の生産性を高める施策が本来求められています。
また、エネルギー政策について、高市首相は、自民党総裁選時から、メガソーラーへの規制強化を訴えてきましたが、同時に、GX投資を推し進め、脱炭素電源を最大限に活用するという従来の政府方針を継続しています。
エネルギーは経済と安全保障の基盤です。日本は、脱・脱炭素政策に舵を切り、官民合わせて150兆円規模にものぼるGX戦略の見直し、再エネ固定価格買取制度(FIT)の撤廃を進めると同時に、原発の再稼働・新増設を進めることなどにより、その場しのぎの補助金策ではなく、強靭なエネルギー供給体制を構築することで電気代低下を推し進めるべきです(*5)。
*1 財務省「財政総論(p.6,2025年11月5日)」より。
*2 伊藤忠総研「日本経済:トランプ関税の影響本格化と住宅規制強化の影響でマイナス成長(2025 年 7〜9 月期 GDP) (2025年11月17日)」より。
*3 実質可処分所得とは、個人所得の総額から税金や社会保険料を除いた、個人が自由に使える「可処分所得」に物価上昇分を加味した指標のこと。
*4 該当する17分野は、AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙、デジタル・情報安全、コンテンツ、フードテック、資源エネルギーGX、防災・国土強靱化、創薬・先端医療、核融合、重要鉱物、港湾ロジスティクス、防衛、情報通信、海洋からなる。
*5 幸福実現党政調会ニューズレター(vol.38)「新しい温室効果ガス削減目標を直ちに撤回し、現実的な「エネルギー基本計画」に見直しを」など参照。
以上
【全文】
詳細は下記のPDFをご覧ください。
PDF 高市政権の目指す「強い経済」は、国民生活を破壊する
高市政権の目指す「強い経済」は、国民生活を破壊する 幸福実現党政務調査会ニューズレター No.40(2025.11.23)